
皆さんがカメラに求める要素ってなんでしょうか。
AF の精度やファインダーの見やすさなど人それぞれだと思いますが、私の場合カメラに求 めているものは圧倒的なルックスです。
どんな時でも首からカメラをかけていないと気が済まない私は、何よりもデザインを、 「持っていたいか」を重要視しています。
普段は SIGMA の fp というカメラを使っているのですが、ファインダーがないことだけが唯 一引っかかっており2台目のカメラとして Leica M11 の購入を検討していました。 しかしどれだけ探してもピンとくる作例が見つからなかったんですよね。 Hasselblad CFV II 50C と迷っていた所だったので一度 Leica がどんなものか試してみよ う、ということでお借りしました。
私が Leica に興味を持つきっかけとなった方がメインで使っているのがこの M10-P でした。 購入するなら M11 か M10-P だと決めていたのですが、検討した結果修理寿命や材質などの 問題から M11 を選択。しかし、M11 と違い TTL 測光であるという点や真鍮製のボディである ということを考えると、このまま一生 M10-P を使わないままになるのはもったいないと感 じたので今回あえて M10-P を選びました。
レンズは Summilux 35mm f1.4 2nd です。いわゆる「球面ズミルックス」とか「pre-asph」 と呼ばれているものですね。
35mm レンズを借りよう、としか決めていなかったので実店舗で Summicron-M 35mm f2 ASPH. と比較させていただきました。最終的には fp につけた時のルックスとその独特の写りから Summilux 35mm f1.4 2nd を貸していただくことになりました。
作例の前に少しだけ外観の話を。
興味ない方はサクッと飛ばして作例まで行っちゃってください。

どうでしょう。
近未来的なデザインの fp に対し M3 の時代からそのスタイルを忠実に継承してきた M11。
見た目だけでここまで惹かれるカメラは今のところ fp と M 型だけです。 fp のようにボディ前面で社名の主張はせず、軍艦部にさり気なく刻まれた“Leica LEICA CAMERA WETZLAR GERMANY”の文字。
引き算の美学とフォントの美しさは fp に通じるものがあります。
Wi-Fi の安定や軽量化を目的としてアルミニウムとマグネシウムが採用された M11 のブラ ッククロームと違い、トップカバーと底蓋に真鍮が採用された M10-P は触ると少しひんや りしています。理由もなく触っていたくなるような妙な安心感がありますね。
本当は「M-P(typ240)と違って前面のフォーカスボタンが黒になったのがイイ!」、とか 「ストラップ取り付け部が少し前についているおかげでレンズを付けても前に傾かない設 計がスゴイ!」とか、言いたいことは山ほどあるのですが本当に書き終わらなくなりそう なのでここでは割愛しておきます。
次はレンズです。
描写傾向についてはまた後述するとして見た目の話から。

fp に装着した時のルックスが本当に素敵ですね。
こちらの Summilux 35mm f1.4 2nd はフォーカシングレバーがプラスチック製だったので後 期型のモデルではないかと推察できます。
少しマニアックな話ですがこの Summilux は 30 年以上製造が続いたモデルで、フォーカシ ングレバーの材質だけでも 4 世代に分けることができます。
個人的にはシャープな見た目の最後期型の物が好みだったので、実際に見せていただいた ときに少しだけ嬉しかったのを覚えています。
余談ですが、このレンズにフィルターを装着するには 12504 というレンズフードを使う必 要があります。12504 は中央で 2 つに分離可能で、シリーズ7のフィルターを中に入れる ことが出来るようになっています。個人的にはフード無しのほうが見た目が好みなので、 使用する際には誤って前玉に触れてしまわないように注意する必要がありますね。
少しばかりの荷物と M10-P、fp だけ持って京都へ向かいます。
M10-P には自前の Voigtländer NOKTON Vintage Line 50mm F1.5 Aspherical II S.C を、fp には Summilux 35mm f1.4 2nd を付けてあります。
35mm と 50mm で二台持ちすることでレンズ交換の手間を省こうという算段ですね。 ここからの作例は基本この組み合わせだと思ってください。
現像は Lightroom・VSCO ですが、M10-P から出てくる画はほとんど完成されています。 過度な味付けはしないように。
まずは M10-P の作例から行きましょう。

あくまで私の使い方ですが、M10-P を使うときはまず ISO ダイヤルを 100・200・400 のどれ かに設定しておきます。これはフィルムカメラ気分を味わえるので。 M 型の ISO ダイヤルは巻き戻しクランクのデザインを踏襲していているからでしょうか、 一度上に引き上げてから回転させる必要があります。
Leica としてもここは頻繁に変更する想定じゃないんじゃないかな。

絞りは基本開放、シャッタースピードのダイヤルで露出を合わせます。ファインダー下部 に表示される露出インジケーターの矢印の方向にシャッタースピードダイヤルを回せば OK。 なんて分かりやすいんでしょう。


一つ注意する点としてはこのカメラ、ハイライトの粘りがなく測光もなんだか気分屋さん みたいな感じです。
余裕があるときは少しアンダー目にして撮っておきましょう。

最近のデジタル M の Raw データは少し独特という話を聞いていたのですが、触っていて驚いたのは特にシャドウ領域。
アンダーで撮って現像時に持ち上げても綺麗に残っています。そしてノイズ感が異常に少 ない。全体的に透明感があって品のある写りをしている印象。

結論から言うとレンジファインダーはすぐに慣れます。
レンジファインダーの最大のメリットは「フレーム外の世界が見える」ということ。

この写真を例に考えます。
動いている人や物にレンジファインダーでピントを合わせるのは至難の業です。 絞れば少し簡単になりますが、地下道というシチュエーションではできれば開放で撮りた かったので勝負に出ます。
まず歩いている人の進行方向で先に構図を決めて中央辺りにピントを合わせておきます。 あとはその瞬間を待つだけ。フレームの外からフレームの中に人物が入ってくるのを確認 して中央あたりに来たときにシャッターを切ります。

緑の出方が少しフィルムライクな感じがしますね。
少し彩度を落とすのが好みかな。


オートホワイトバランスが少し独特なのもまた味になります。




光学ファインダーなので背面ディスプレイを確認するまではどんな写りか分かりません。
しかしこのカメラは想像していた写りを遥かに超えてきますね。
撮ってプレビューを見たときに嬉しくなれるカメラっていいカメラだと思います。
正直、実際に使ってみるまで「ボディのクオリティーが高いだけで、写りは国産機とそこ まで変わらないだろう」と思っていましたがそんなことはなかったみたいです。 もちろん万能なカメラではありません。AF なんてないしハイライトはすぐに飛ぶし。 レンジファインダーで時間をかけてフォーカスを合わせて丁寧に露出を調整しないとすぐ に失敗します。
でもそんなダメなところも含めて愛して欲しい。そんなカメラです。
さて、ここからは SIGMAfp+Summilux 35mm f1.4 2nd の番です。
この Summilux、実はかなりのクセ玉です。
まずはこの作例を見て欲しい。

ミスト系のフィルターなしでこの写りです。
神秘的…とでも言いましょうか。ハイライトが綺麗に滲んでいます。
この日はすごく暑かったのを覚えています。
すごく抽象的な表現ですが、夢の中にいるような感じがしますね。
なかなか場面を選ぶレンズだと思いますが、ここぞという時に使うと引き込まれるような写りをしてくれます。悪くない。

奈良の浮見堂です。
このレンズ、開放から一段絞ると突然シャープで端正な写りになります。


開放の独特な滲みを味と見るか弱点と見るかは使い手次第だと思います。 それを表現の一部として活かせるかどうかが、このレンズの面白さでもありますね。

というわけで Leica M10-P と Summilux 35mm f1.4 2nd の簡単なレビューでした。 現行品は 100 万円以上するデジタル M 型ライカを使うという経験は、非常に貴重なものに なりました。最新のミラーレスカメラに搭載されているような高速 AF や高性能なファイン ダーは搭載されていませんが、このカメラは他にない貴重な撮影体験を与えてくれます。 伝説的な存在となった初代 M3 の時代からそのスタイルを継承し続けている Leica には敬意 を表せざるを得ません。
Leica の M システムを手に入れることは、ただカメラを手に入れることではなく歴史を、 遺産を手に入れることだと思うのです。
最後は少し気取ったような文章を書いてしまいましたが、そんな気にさせてくれるくらい 素晴らしいカメラなんですよ、本当に。
貴重な経験をさせていただけたことに、この場を借りて心からお礼申し上げます。





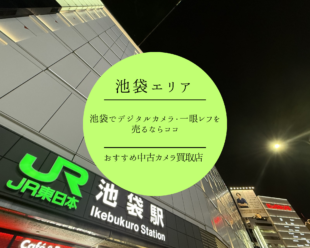
タイトルは某雑誌から。 心からSIGMAを愛しています。 写真に真摯に向き合いたいです。
足代悠惺の使用カメラ
足代悠惺の使用レンズ
タイトルは某雑誌から。 心からSIGMAを愛しています。 写真に真摯に向き合いたいです。
足代悠惺の使用カメラ
足代悠惺の使用レンズ